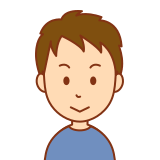
老人保健施設に就職するかどうか迷ってる。メリットやデメリットがあれば参考までに聞いてみたい。

理学療法士が老人保健施設で働くメリット・デメリットについて、それぞれ5つ挙げてみました。あくまでも私見ですが、最後までお付き合いいただけたら幸いです。
はじめに
異動や転職を含めると、整形外科病院→クリニック→個人医院→老人保健施設→訪問看護ステーションを経験してきました。人によってメリットとデメリットの感覚は違うと思いますが、ひとまず私が経験して実際に感じたことをお話させていただきます。
メリット①:比較的ゆったりまったりと仕事ができる
基本的に急性期の病院やクリニックほどの慌ただしさはなく、維持期特有の比較的ゆったりした時間が流れています。入所者さんの状態はわりと落ち着いているし、目まぐるしく入れ替わりがあるわけではないのがその理由です。
ただし、介護老人保健施設には「その他型」「基本型」「加算型」「強化型」「超強化型」などの施設区分が存在する都合上、一生懸命に短期集中リハビリテーション実施加算や認知症短期集中リハビリテーション実施加算などを取っている施設があります。これらの加算業務が重なると、リハビリテーションスタッフもなかなか忙しくなります。
加えて、どこの施設も介護職員の人員不足が深刻です。そうなると現場はややピリつくし、たまに介護業務の応援に向かわなければならないときがあります。全員でなんとかしようという空気感があるので、人員不足の影響がリハビリテーションスタッフまで波及してきます。
改めて振り返ってみると、老人保健施設には老人保健施設なりの忙しさがありますねこれは…。
メリット➁:他職種から学べることが多い
老人保健施設に限ったことではないかもしれませんが、作業療法士や言語聴覚士から専門的な知識を学ぶ機会が多いです。特に高次脳機能障害について、やはり彼らはよく知っています。
「あの人はこういう障害だから、こんな症状が出ている」とか、逆に「あの症状は、こんな障害が考えられる」とか「認知症とはこういうもの」とか「障害の影響もあるけど性格的な影響もある」とか。私もたくさん教えてもらいました。おかげで今まで理解に苦しんでいた人間の「ソフト面」について学ぶことができました。余談ですが、MMSEも習得することができました。
メリット➂:ソフト面での学びが多い
個人的にはソフト面での学びが多いのが一番のメリットだと思います。ここで言うソフト面とは、いわゆる人間性というか性格、高次脳機能や精神状態について。さらに家族や生活の質について、人生とは?生きるとは?などというちょっと哲学的な部分のことです。
私だけかもしれませんが、理学療法士はどうしてもハード面(ここでは身体構造や機能のこと)にばかり目が行きがちです。でもね、特に老人保健施設ではハード面にばかり目を向けていても正直言ってジリ貧です。身体機能だけ良くしても、ぶっちゃけ問題の解決にはなりません。
どちらかというと、やはりソフト面への見識や理解が重要と言えます。「あの人は元々こういう性格で、ある部位に高次脳機能障害がある。あの発言や行動は性格的な部分もあるだろうが、高次脳機能障害がそれを助長している。家族にはそれらも含めて理解してもらわないといけない。生活環境はああしてこうして、生活の質はどうやれば担保できるのか。」など。
そもそもリハビリテーションとは、ハード面よりもソフト面の意味合いのほうが近いと言えます。老人保健施設ではリハビリテーションの意味を深く考えるきっかけとなるでしょう。
デメリット①:書類業務やカンファレンスが多い
リハビリテーション実施計画書を1回/3ヵ月は必ず書かなければならず、その度にカンファレンスが開催されるため時間が取られます。担当人数分を作成するのって意外と大変なんですよね。
他にも加算関係の書類ならなんやら、何かにつけて書類業務があります。必要だからと言われたらそれまでですが、なんだかなあと思いながら過ごしていた気がします。
老人保健施設ではリハビリテーション自体の忙しさよりも、こういった書類業務やカンファレンスに奪われる時間のほうが多いように感じます。それにしても書類業務って、本質的には何の意味もなさない作業だと思うのは私だけでしょうか。
デメリット➁:モチベーションの維持が大変
病院やクリニックの経験者だと、なおさら感じるかもしれません。入所者さんは基本的に超高齢者で、抱えている疾患は様々ですがほとんどが維持期です。したがって、急性期のように明らかに良くなる変化は少ないのが現状です。
罹患期間が長いことに加え、入所者さんによっては高次脳機能障害(発動性の低下や意欲低下など)が合併しているため、本人たちのモチベーションも低めな場合が多いです。さらに各々の事情により、みんなが在宅復帰できるわけではありません。いわゆる「行く先」がなければ、モチベーションが上がらない気持ちもなんとなくわかります。
老人保健施設はこういった条件下で働くことになるため、こちらのモチベーションを維持するのも大変です。わたしがモチベーション維持のために意識していたコツをざっと挙げると「小さな変化に気づく」「病院やクリニックの感覚を捨てる」「私生活をさらに充実させる」といった具合でした。
デメリット➂:急性期への転向が大変(かもしれない)
急性期から維持期に転向した私がいるように、逆に維持期から急性期に転向する人もいるでしょう。患者(利用者)さんを診るのは同じとはいえ、急性期と維持期では求められるモノが異なります。主観としては、おそらく急性期への転向は苦労すると思います。
当然と言えば当然ですが整形外科疾患では身体構造や機能、脳血管疾患では脳の構造や機能、内科疾患では臓器の構造や機能の知識が必須です。これができないと医師の会話についていけないばかりか、患者さんへの説明もできません。さらに治療技術的(手技的)な問題も出てくるでしょう。対して維持期では、正直言って知識や技術が足りなくても全然なんとかなります(本当は良くないです)。
もちろん個人の力量によるし、時間をかければなんとでもなります。急性期だって維持期での知識が必要な場面はたくさんあるので、これまでの経験が決して無駄になることはありません。とはいえ、やはり最初はどうしても苦労するでしょう。
急性期は忙しいです。バタバタしています。そんな環境で急性期に必要とされる知識や技術を習得するのは、なかなか骨の折れる作業なのです。
おわりに
老人保健施設で働くメリットは「比較的ゆったりまったりと仕事ができる」「他職種から学べることが多い」「ソフト面での学びが多い」、デメリットは「書類業務やカンファレンスが多い」「モチベーションの維持が大変」「急性期への転向が大変(かもしれない)」です。
どこで働いてもメリット・デメリットは存在するでしょう。結局選ぶのは自分なので、何をどこまでなら許容できるのか、デメリットを上回るメリットがあるのかなど、就職前にできるだけ考えておきましょう。
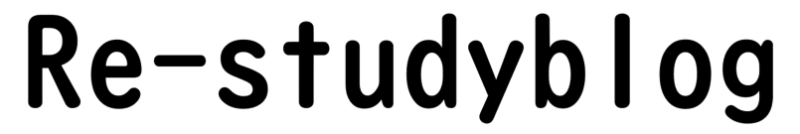





コメント