
夫が交通事故で頭を強く打ってしまった。今のところ大丈夫そうだけど、後遺症の心配はいらないのかな。

ただちに後遺症が出るかどうかは何とも言えませんが経過観察は必要です。交通事故による後遺症の一つに高次脳機能障害がありますが、その中でも前頭葉症状に絞って解説していきます。
※以前、認知症専門医のもとで勉強していました。ここでは認知症に関して得られた知見、そのほか調べていて気になったことを少しずつ公開していきます。
高次脳機能障害:前頭葉症状について
交通事故ではその特性により、前頭部を強く打つけることがあります。そのため、脳の機能障害(=高次脳機能障害)も脳の前方(=前頭葉)に由来するものが多く、いわゆる「前頭葉症状」が出やすい傾向にありあます。
主な前頭葉症状は「注意障害、遂行機能障害、記憶障害。行動と感情の障害」です。こういった症状は本人のQOLを下げるだけでなく、ご家族の負担を重くする要因にもなります。
高次脳機能障害は事故後間もなく発症することもあれば、数年あるいは数十年後、びまん性に進行したのちに発症することもあります。頭部MRIなどではっきりとわかれば対応しやすいのですが、都合よく画像所見として現れないこともしばしばです。
症状に対して敏感になり過ぎるのも問題ですが、後遺症の存在は頭の片隅に留めておくべきだと思います。もしかしたらと思ったら、専門医への受診を強くおすすめします。
各症状の説明に例を挙げて解説します。聞き慣れない単語が多いかもしれませんが、少しでも参考になれば幸いです。
注意障害
前頭葉症状で現れる注意障害には、以下の4つのパターンがあります。
- 選択性注意:注意を一点に集中する能力
騒がしいところで特定の人と話ができない、飽きやすい。 - 持続性注意:注意を維持、持続させる能力
長く仕事をするとミスが出る。 - 配分性注意:複数の刺激に対して同時に注意を向ける能力
複数人での会話ができない。 - 転換性注意:注意の方向を転換する能力
話題が変わるとついていけない。
注意力とは「ある一つの事柄に気持ちを集中させる能力」を示す意味合いが強いですが、細かく見ると上記のように分けられます。注意力は日常のあらゆる知的活動の基盤となっているため、注意障害があるとおおむねすべての生活に影響が生じてしまいます。
遂行機能障害
遂行機能とは目的をもった一連の活動、 たとえば料理などの家事動作を効果的に行う能力のことを言います。
- 心の中で目標を決める
お味噌汁を作ろう。 - 手順を考える(計画=段取り)
具材は豆腐・わかめ・油揚げを入れよう、出汁は煮干しにしよう、お味噌は赤がいいな。鍋を用意して、水を入れて沸騰させている間に具材を用意すればスムーズかな。 - 複数の方法から取捨選択をする
いや待てよ、やっぱり時間がないからインスタント味噌汁にしようか。 - 実行する(決断)
インスタント味噌汁にお湯を入れる。 - その結果を確認する(フィードバック)
しっかり溶けたかな。よし食べよう。
ちょっとヘンテコな例ですが、なんとなくイメージできますかね。普段なにげなくやっている行動の一つ一つには、このような遂行機能が関わっています。
遂行機能が障害されると、日頃の生活や作業を自分で組み立てられなくなります。行動を計画的に行うことができない、優先順位が決められない、行き当たりばったりの行動になってしまうなどの症状があらわとなります。
ただし一つの行動を指示されて、一つ実行することは可能です。アドバイスがあればできるんです。問題になるのは複数の行動の順序や手順を考えなければならない状況で、段取り良くふるまえなくなることです。完全に本人に任せてしまうとうまくいかなくなります。
記憶障害
記憶を司る脳の一部(=海馬)が損傷すると、事故前後の記憶が障害されることがあります。記憶障害といえばアルツハイマー型認知症が思い浮かびますが、このような退行性変化だけではなく、事故の後遺症として記憶障害が生じることもあります。
- 逆行性健忘
事故以前の記憶が思い出せません。回復するにつれて徐々に事故時まで思い出せるようになります。 - 前向性健忘
事故以降の新しいエピソードが記憶できなくなります。 - 展望記憶
決まった時刻で約束が果たせないなどの将来に向かって行う記憶のことをいいます。たとえば「プレゼンの締め切りは2月末だ」というように、未来に起こることについて憶えていられなくなります。
行動と感情の障害
行動と感情の障害では「抑うつ状態、興奮状態、意欲の障害、情動の障害」が顕著に現れます。具体的には以下の3パターンです。
- 発動性の低下
意欲の低下、引きこもり、うつ状態など - 脱抑制
暴力、暴言、自己中心的、衝動性など - 自己内省の問題
病識の低下(自分を客観視できない/自分の状態を正確にとらえられない)など
一言でいうと「人格変化」です。対象者と接しているとおそらく一番わかりやすく、且つ一番大きな問題となり得る症状です。このような症状は明らかに社会性の低下をもたらします。
行動と感情の障害は脳に損傷がなくても事故による心因性の要因で現れることもあるため、なかなか解釈が難しいところです。
高次脳機能障害と診断するには、これらの症状を説明しうる脳の損傷(=器質的損傷)があることが条件です。器質的損傷を判断するには画像所見(CT、MRI)が有用ですが、軽度外傷性脳損傷では必ずしも画像上の異常を認めないことがあります。
まとめ
交通事故による後遺症として高次脳機能障害があり、今回は前頭葉症状(注意障害、遂行機能障害、記憶障害、行動と感情の障害)に絞って解説しました。
交通事故後間もなく~数十年単位で「なんだか変だな」という感覚を覚えたのなら、もしかしたら前頭葉症状かもしれません。専門医(神経内科)への受診を強くおすすめします。
参考文献
渡邉 修:交通事故後の高次脳機能障害, Journal of the Japanese Council of Traffic Science Vol.17 No.1 2017
博野信次:臨床認知症学入門 改定2版, 金芳堂, 2007
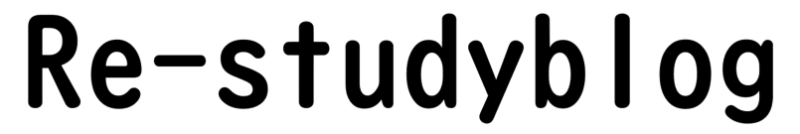



コメント